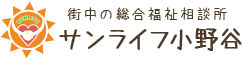トピックス




6月末の半期決算、新規事業の実地指導(監査)を終え、この度、6名の新たな管理職を任命させていただきました。
着実にキャリアパスの階段を昇られている方、はじめて管理職に就かれる方などいましたが、みんなどこか初々しい表情でした。
実は今年で25年目を迎えるサンライフ小野谷は、すべての部署で業務改革や経営改革が進んでおり、極めてエポックメイキングな年と言えます。
この重要な節目にあたり、任命された若手(中堅)職員は全て、わが社が誇る優秀な人財です。
新たな事業計画や、目標を聞きましたが、どれも意欲的で、モチベーションにあふれ、とても嬉しく感じる所信表明でした。
私から「福祉の仕事に携わるきっかけは、おそらく全員が‘感謝されること‘への喜びがあると思います。それぞれの役割が地域福祉につながり、多くの笑顔を生んでいると確信し、初心を忘れず次の25年に向け頑張りましょう」と激励させていただきました。
この夏も新たなAIのチャレンジをしています。
ひとつは、介護技術のひとつをAIで予測してケアの充実を図るアプリの開発にかかわること。日々、個別ケアと言いながらも淡々と繰り返すケアをAIに分析してもらい、事前に早めにアプローチすることで、ご本人も介護者もトラブルなく楽に暮らせる・・・開発段階から我々の声を活かしてもらい、アプリは製品化にむけラストスパートのようです。
二つ目もAIによる文字起こし、文章ソフトで→そこから発展したアセスメント、モニタリングなどケアマネジメントのプロセスを網羅し、提案型の課題解決を図る機能を加えたもの。現状の様々な専門的支援を文字化する作業から関わらせてもらいます。これも専門職それぞれの最大公約をみつけるためにAIを活用するという合理的な作業。蓄積されたデータをツールにどこまで効率的になるか楽しみです。
三つ目は地元の学生が考えたChatGPTでコミュニケーションの充実を図り、利用者の笑顔を引き出し、スタッフの負担を減らす研究というもの。若者らしい斬新なアイディアで、これも利用者にどこまで変化がみられるかとても楽しみです。
すでに日常生活に身近に入り込んでいるAIを更にうまく活用し、我々の日々の介護業務最適化に活かせないか?チャレンジです。
介護におけるAIは「愛」にもなりうる・・・そんな時代ももうすぐそこかも???


育休中の訪問看護師さんが第2子を連れて来所。ママは復帰の打合せで忙しいので、あかちゃんは入居者とスタッフが預かります。
今回も、泣くことなくみなさんへのお披露目に協力してくれて、本当に愛らしい姿をみせてくれました。
どんなに楽しいレクレーションもリハビリも、この子の笑顔には勝てません・・・。赤ちゃん本人もまるで自分の役割を知っているような・・・。
大きくなってもまた遊びに来て、みんなを笑顔にしてください!!



初夏のいちばん過ごしやすい日が続き、こんなとき、たまには豪華にランチでもと、ステーキレストランへ
若いころは日本全国を旅しながら、研究してきたというお二人からは、さすがグルメという食レポをいただいたという。
これからも、「日々の楽しみ=食べること」を求めて市内にもっと美味しい場所が増えることを願っています。