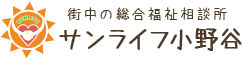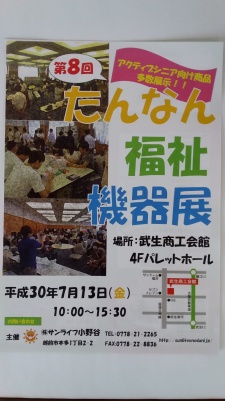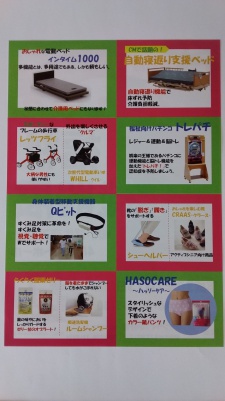トピックス
6月17日(日)10:00~待ちに待ったこの企画「あおいケア代表 加藤忠相さん講演会」が開催されました。先月の映画「ケアニン」上映から約3週間。映画のモデルとなった方が実際に越前市に来てくれたのです。
企画は金剛院の諏訪さんや、月岡医院の方々、越前市文化センターさんらと実行員会を立ち上げ、準備をすすめてきました。先月の映画は700人以上の方々が来られ、学生から当事者、ご家族までその関心の高さがうかがえました。当日ももちろん満席で、いすが足りなくなるほどでした。
サンライフのスタッフ(数名)は昨年も一度講演を聴く機会があり、高齢者ケア(=認知症ケア)の画期的な取り組みや、ユニークな手法、そしてケアに携わる者としての基本的な考え方を目の当たりにし、とてもモチベーションが上がったことを覚えています。
映画ケアニンで描いた「若い介護職の葛藤」が、加藤さんの事業所で現実としてどのように解消され、理想的な施設に変わっていったのか?とてもわかりやすく、面白くそのプロセスを追ってもらえたので、自身の施設での課題をじっくり考えられる講演でした。
講演のあとは、一緒に昼食をとることができ、更に深くその思いをうかがうことができました。短い時間でしたが、全国(今や世界)に注目されるだけあって、これまでのプロセスには深い根拠があり、たくさんのエピソードがありました。そしてとっても気さくで面白く、魅力的な方でした。
とにかく発想を転換させること/科学的エビデンスをもとに/意図的に有機的作用を生み出すこと/この仕事の良さやりがいを見つめなおすこと・・・など多くの学びを得ました。「地域包括ケアの実践」ができる事例として大きな刺激です。
このような貴重な機会を、多くの人と共有できてとても有意義でした。金剛院さんはじめ実行委員のみなさんの熱意のおかげです。今後も事業所の枠を超えて、この講演で得た学びを一緒に実践できたらと思います。本当にありがとうございました。
今年2月に実施された越前市虐待防止研修の第2弾が6月14日(木)@アルプラザで開催されました。
3回シリーズで行われるこの研修ですが、今回も企画段階から講座、ファシリテーターで協力させていただきました。
介護保険制度が4月から改正され、虐待+身体拘束防止について厳しい規制ができました。市内の多くの事業者(管理者)と、行政の皆様とこの改正法について中身を検証し議論する機会となりました。
虐待や身体拘束を防ぐ取り組みは、管理者がただ「防止しなさい」と唱えるだけでは浸透しないもの。
自立支援のため、不必要な行動制限をなくすため、正しい認知症ケアを普及させるため・・・様々な意図があると思いますが、現状や方策を間違えると、管理者が従事者に厳しい指導を押し付け、逆に不適切な支援を誘発し、虐待が増加する恐れがあります。
今回のように皆さんで事業者の枠を超え、現状を共有し、アイディアを出し合い、虐待(身体拘束)防止から質の高い支援つながるように議論しあえたらと思います。
昨日は、NHKで「鶴瓶の家族に乾杯」が放映されましたが、なんと舞台は越前市。
オープニングでは鶴瓶さんと長瀬智也さんが登場し、蔵の辻周辺でロケされていました。広小路商店街からちらっとサンライフの建物が映って、そのあとも周辺の商店街や知っているお店、知っている人が続々と登場し、とても感激しました。今日は、朝からその話題でもちきりで盛り上がりました。
そんな蔵の辻では6月3日(日)に毎年恒例の「太神楽」が行われ、初夏の猛暑の中、いつもの演舞を観ることができました。「昔を思い出すねえ」と暑い中でも見入ってしまう面白さですが、写真をまとめている今、こんな日に鶴瓶さんや長瀬さんが来てくれたらよかったのにと思ってしまいました。