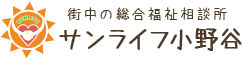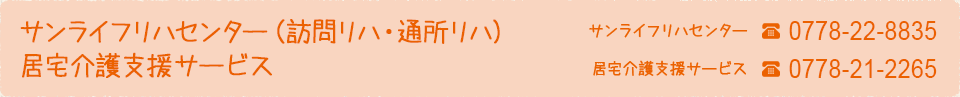トピックス



8月も残りわずかですが、学生の皆さんにとっては9月まで続く夏休みの中盤であり、実習やインターンシップに来てくれる時期でもあります。
ありがたいことに毎週のように学生さんがいてくれるので、何をするにも華やかで、若い力が加わっていつもより楽しい雰囲気です。
入居施設/厨房/在宅(訪問)/通所(デイケア)とそれぞれの場所を一通り体験してもらい、職場や福祉の仕事に触れてもらうのですが、昨年まで学生だった職員や、同じようなインターンシップをした若手職員が説明する立場にいて、指導コメントなどを書いてくれたことも嬉しいことでした。
自分の仕事を説明したり、学生の質問に答えたり、利用者さんとのコミュニケーションを促したり・・・。学生さんにとっても貴重でしょうが、我々スタッフにとっても貴重な時間でした。
実習生のみなさん、お疲れさまでした。最後のあいさつでは感極まって利用者さんや職員への感謝を言ってくれて、こちらも感動してしまいました。
ここでの体験を活かして、素晴らしい社会人になってください。ガンバレ若者!!

7月29日(土)に東地区支えあい推進研修会に参加してきました。
民生委員さん、福祉推進員さん、家庭相談員さん、越前市長寿福祉課のみなさん(地域支えあい推進員)など東地区の福祉に携わる方が一堂に介する研修会で、会場は東地区の本当に多くの方が集まっておられ、真夏の午前中は熱気ムンムンでありました。
特別講演として東京から「さわやか福祉財団」の高橋望先生の講座もあり、地域福祉推進のノウハウを学ぶグループディスカッションも組まれていました。サンライフとしては、家族介護者交流事業として5月の研修報告や、6月のサロンの報告をする機会をいただきました。
さわやか財団の高橋先生と控室で雑談させてもらいましたが、越前市の特に自治振興会を中心とした活動の素晴らしさを強調されてまして、介護予防というスローガンが今年から保険制度上のメニューになり、越前市は土壌があり強みがあることを教えてくれました。
この土壌のうえに、事業所としても積極的に役割を持ち、「支えあい」に協力すればより進んでいく。家族介護を支援するという一つのメニューですが、専門職としてその役割は大きい。虐待や凄惨な事件を防ぐこと、子どもや療育、在宅障がい者、不登校、引きこもりなど地域の多様な課題を知る・・・など多くの考え方を共有させてもらいました。
東地区の様々な福祉活動に、事業者として、専門職として参加させてもらえましたことに改めて感謝です。
ちなみに8月もサロン(家族介護の交流の場)をします。6月は14名の方が参加してくださいました。チラシを見て、お気軽にご参加ください!



越前市の高齢者福祉メニューのなかに、「家族の介護」を支援する事業があります。題して「家族介護者交流事業」。読んでその名の通りなのですが、今回第1回目の交流企画を行いました。初めての企画だったので、いろいろと心配でしたが、多く方に参加していただき、おおむね成功に終わったのではないかと思います。
家族介護者は、孤独であること、いつまで続くか先が見えない、無償であること、家族であるが故のストレス・・・様々な困難を抱えておられます。我々が「仕事」として、「有償」で介護支援をしているのとは全く違う。「誰にも吐き出せない」状況が続き、介護者の疲弊につながり、虐待などの大きな問題に発展するケースも珍しくありません。
この事業は、被介護者ではなく、そんな介護者同士が集い、お互いの悩みの共有や情報交換の場になることがいちばんの目的でした。
当日は、ハンドマッサージや全身マッサージ、足つぼ、ブラジル本格珈琲とスイーツのカフェなどを用意し、それぞれの情報交換が進むような雰囲気を作っていきました。その効果もあり、介護者同士で話をしたり、施術中に専門職にアドバイスを求めてくださったり、嬉しい場面がたくさんありました。
在宅で、家族で介護を続けることの大変さは、ご本人でないとわからないものです。
ちなみに、全国では家族介護者=ケアラーと呼び、高齢者だけでなく、在宅障がい者、障がい児の子育て、育児などとにかく家族で無償の支援を続ける方への支援を広げ、法制化しようという動きも出ています。
サンライフもこのケアラー支援の一端が担えるよう、少しずつ貢献できるよう頑張っていきたいと思います。まずは第1回参加してくださったみなさんありがとうございました。