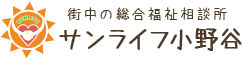トピックス


7月に入り、続々と施設見学に来ていただいております。
新型コロナウィルスの影響で、大人数の説明会は控える中で、2021年4月の新卒採用にむけた準備は佳境に入っていまして、弊社でも貴重な戦力となりうる若い学生さんが少しずつ来てくれています。学生の説明をするのは、今年2年目~4年目の新卒で入社した先輩たち・・・。彼女たちが入社した時の初々しい姿を写真をみると感慨深くなってしまうものです。今や説明し、指導する側にたって、堂々と振る舞っているので頼もしい限りです。
私自身、就職氷河期世代であり、働く場所を選ぶのは本当に大変でしたが、今の時勢はそれ以上に情報があふれ、価値観が多様化する時代であり、学生さんの大変さが伝わってきます。
福祉医療業界に来てくださる若者はとにかく財産です。様々な体験をして、比較して、選んでいただけるよう精いっぱい対応したいと思います。




今年度は4月より、いろいろな企画を中止・縮小してきましたが、「サービス質向上委員会」でも、全部署職員を対象にした大人数の勉強会がコロナウィルスによる3密制限の影響を受け中止。部署ごとの小ぢんまりした会にせざるを得なくなりました。ところが、今回その「こぢんまり」を逆手にとった施設介護職(K君)の企画は少人数で中身の濃い勉強会になり、いつもよりも充実した研修になりました。
メンバーは新入社員と入社2年目~4年目の若手、入社6年目の中堅職、リーダーが参加しました。撮影係として参加した私は、内容があまりにも良かったので、詳細にメモをとりましたので報告書風にしたいと思います。
・写真をみて介護職としての気づきを議論
とある利用者の普段の写真をみて、どんなことを気づくか意見を出し合いました。介護職ではない私としては、何の変哲もないいつもの写真だと思いましたが、その方の姿勢や車いすなどの問題点が出され、「へ~なるほど」と思っていると、中堅職からは更に細かな気づきが出されました。特に服装、季節や気温にあわせた配慮、表情など「そんなところまで見ているんだ」と感じる気づきがあり、「本人の立場になったら」「自分が家族だったらどう思うか」というアドバイスが胸に響きました。
「毎回一個ずつでも気づき、配慮することを「クセ」にすることが大切。思いを表出できない利用者も多い。自分がされて嫌だ思うこと、それを言えない利用者の気持ちに気づくことで改善され、QOLが上がっていくんだよ」・・・というアドバイスにもはや感激してしまいました。
・服を着せる介助を実際にやってみる
ねじれた袖、着心地、組合せ、デザイン、見た目など服を着ていただく介助ひとつでも多くの視点がある。自分が服を着る時と同じように直すこと。「介護技術は経験を積めば自然と上がっていくが、人として当たり前の配慮は意識しないと身につかない」ある先輩は時間がかかっても丁寧にケアしている。気づいても「まいいか」としないで「ちゃんとしてるね」と言われるようになってほしい・・・ここから新人のリアクションも更に真剣になっていきました
・入社してこれまで悩んだこと、怒られたこと、泣いたこと
講座が終わって座談会になり、入社5年の間に経験したことを話してくれました。認知症ケア、介護抵抗、多職種からの指摘、自信がなくなっていく毎日・・・様々な壁にぶつかって、心が折れ、泣いた経験も吐露してくれました。休日でも仕事のことを考え、表情の暗さを指摘されたこともあったという。そんなとき先輩に「できないことはできないと言わないと辛いよ」と言われ心が救われ、楽になったと言います。
「苦手」「つらい」「できない」という気持ちは、~人を真剣に支援しようとするとき生じる当たり前の感情~であり、それをためないで正直に表出することが大切。「わからないことを聞く」という単純なことができない時期もあり、それを共感しつつ「介護という支援は「〇×(マルバツ)」の仕事ではない。日々の積み重ねが答えをくれる・・・」今まさに壁にぶつかっているであろう3人の若手それぞれに響くアドバイスでした。
今回長々と書き連ねてしまいましたが、今回の勉強会は私の手帳が真っ黒になるほど勉強になるアドバイス、言葉でいっぱいでした。今回参加しなかった全職種・全スタッフがサービスの質を上げるために日々努力していることを忘れてはならないと思いました。






緊急事態宣言が解除された今週より、施設では少しずつ少しずつ日常に戻りかけております。
1か月続いた勤務体制は通常シフトに戻り、在宅勤務で出された「宿題」を提出するという、職員も学生と同じような境遇を味わっていますが・・・
会議も少人数で3密を避けながらも徐々に再開されはじめ、昨日は、施設管理職が今回の緊急事態にどう対応したのかを振り返りました。
外出、面会制限/リハビリ、レクリエーションの工夫/2交代制の食事/1日数回の消毒作業/職員の外食禁止令/・・・どの対策がどういう効果を生んだか?課題があったか?整理しました。
介護施設での「院内感染」では、命にかかわること、運営の存続にかかわる重大な事態が見られ、対策はどうしても「制限」が多くなりましたが、一方で様々なアイディアも出されました。徹底した感染対策からか入居者もスタッフも体調不良がほとんどなく、普段よりも健康に過ごせたように思います。ご家族へお手紙を書いたり、LINEやTV電話でコミュニケーションを図ることもスムーズになりました。食事はお弁当が中心となりましたが、中には近所の居酒屋さんのテイクアウトを利用したり、買い物や配達を利用して食事を楽しむ人もいました。今回のこうした対策や効果の検証、マニュアルはまた必ず活かせると思います。
月曜よりリハビリ体操や内職作業は再開され、長い非日常生活から解放されたすがすがしいみなさんが見られています。「なんでもないようなことが幸せだった」と誰かが言っていましたがその通り!!何事もなく過ごせる日常に感謝し、慎重に気を緩めず過ごしていきたいと思います。
*期間中に差し入れのお菓子、マスク、激励のお手紙など地域の方よりたくさんいただきました。本当にありがとうございました!!


5月15日に、サンライフに勤めて15年のMさんが退職されました。15年といえば・・・サンライフの施設ができたのが平成16年。Mさんはその翌年の平成17年からずっと勤め続けてくれました。まだ入居者もスタッフも少なく、会社としてよちよち歩きだったころです。
Mさんは御年75歳。自分が利用者になってもおかしくない・・・と笑っていましたが、まだまだ若いものに負けないエネルギーやバイタリティがありました。もともとは福祉業界とは無縁の世界におられましたが、15年間常に利用者のことを第一に考え、丁寧に、温かく接し、介護職に負けない支援を続けてくれました。加えて明るいMさんは本当に愛されていました。その証拠に最後の日のセレモニーでは、姿が見えなくなるまで拍手が続きました。
最後の出勤では昔がよぎったのか、思い出に残った利用者のことをたくさん話してくれました。特に支援が大変だった入居者のこと多かったですが、それでも懐かしそうに当時の苦労を語っていました。
福祉の仕事は専門性が大切ですが、やはりそれよりも大切なのは「人間性」だと思います。「困っている人を助ける」という基本的な姿勢を持ち続け、理屈や理論ではないハートが重要だということをMさんは教えてくれたように思います。
会社運営についても、ルールや組織づくり、危機管理、待遇の改善など、経験と年齢からくる含蓄ある提案もしてくれました。本当に貴重な先輩で、人財でした。言い尽くせないほど感謝しています。
まだまだお元気で活躍されることと思います。いろいろお誘いしますので、これからもサンライフに関わって、また(やさしく)叱ったり注意してください。ありがとうございました。